
こんにちは、キクです。
本記事では、僕が今週読んだIT系のニュースについて「振り返り」と「まとめ」を目的として整理していきます。
本記事の内容
- 記事1:ネットアップ、「NetApp INSIGHT 2025」でAI時代のデータプラットフォーム戦略を強調
- 記事2:供給電力容量2万2400kW・総工費約600億円…KDDI、ロンドンに新DC
- 記事3:レノボの「Neptune」水冷サーバーとニデックのCDUがタッグ、AIデータセンターの省エネ化を推進
- 記事4:KDDI、大阪堺データセンターを2026年1月稼働開始
- 記事5:小さな不具合が引き起こした大規模インターネット障害、AWSの事案から学ぶ教訓
- 記事6:Gmailのパスワード、流出した1億8300万件のアカウントの一部として確認される
- 記事7:デジタル庁が後押しする「第三者保守」 コスト削減と投資転換を実現する6つのユースケース
記事1:ネットアップ、「NetApp INSIGHT 2025」でAI時代のデータプラットフォーム戦略を強調
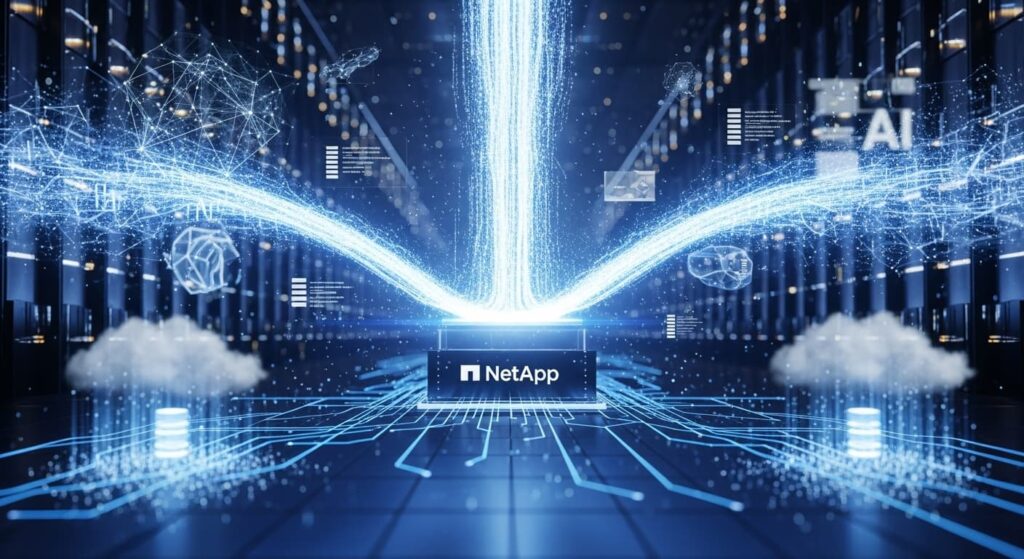
NetAppが年次イベント「NetApp INSIGHT 2025」において、AI時代に即したデータプラットフォーム戦略を発表し、企業のデータインフラ変革を強調した
戦略4領域への対応
NetAppは、AIイノベーション、データインフラモダナイゼーション、サイバーレジリエンス、クラウド・トランスフォーメーションという4つの課題に対し、データプラットフォームで応えると説明している
- あらゆるワークロードにAIが不可欠という認識
- 「AIレディなデータ」の欠如がAIプロジェクト放棄の原因とされる
- 企業インフラが抱える統合・運用・セキュリティの課題を整理
新プラットフォーム構成と製品群
同社のデータプラットフォームは「ユニファイドストレージ」「データマネジメントサービス」「インテリジェントエクスペリエンス」の3層で構成されており、注目製品も発表された
- 「NetApp AFXシリーズ」AIワークロード向けに設計されたディスアグリゲーテッド型オールフラッシュストレージシステム最大128ノード、データセット容量1EB以上、毎秒4TBスループット等を特徴としている
- 「NetApp AI Data Engine(AIDE)」データ収集~準備~展開までのAIデータパイプラインを効率化、冗長コピー削減・最新データ維持・ガバナンス機能を提供
- ハイブリッド/マルチクラウド向けのデータモビリティ強化クラウド向けストレージやグローバル名前空間機能を拡張
インパクトと注目点
NetAppは、AIデータ活用を支える「データプラットフォーム」そのものを差別化要素と位置付けており、製品発表を通じてエンタープライズAI市場への参入意欲を明示している
- データ準備に多くの工数を費やしているという実態を受け、効率化を訴求
- ハードウェアだけでなく、ソフトウェア/サービス面に重きを置いた戦略が鮮明になっている
- AI用途でのストレージ性能・拡張性・安全性が競争軸になる可能性
おわりに
NetAppの今回の発表は、単なるストレージ強化にとどまらず、AI時代におけるデータ活用インフラの“場”を再定義する動きと捉えられる
企業がAIを本番運用に移す際の障壁として「データの準備・運用・管理」がある中で、NetAppはその部分に対して明確な解法を提示している
今後、実際の導入企業動向と成果にも注目したい
ネットアップ、「NetApp INSIGHT 2025」でAI時代のデータプラットフォーム戦略を強調
記事2:供給電力容量2万2400kW・総工費約600億円…KDDI、ロンドンに新DC

KDDI傘下のテレハウスヨーロッパは、生成AI需要に対応するため、ロンドンに新たな高電力データセンターの建設を開始した
新DCの概要
新施設「テレハウス・ウエスト2」は、ロンドン市内のドックランズ地区に位置する
- 総工費は約600億円
- 供給電力容量は2万2400kW
- 敷地面積は約3万2000平方メートル、地上10階建て
- 2027年度の開業を予定
立地と戦略的意義
新DCの立地はロンドンの金融街に近く、アクセス性が高い
- 既存の「ロンドン・ドックランズ・キャンパス」の6棟目
- キャンパス全体の電力容量は5万7100kWに拡大
- 世界最高クラスのコネクティビティを誇る拠点
成長するロンドン市場
生成AIの影響で、ロンドンのDC市場は急拡大が見込まれている
- 今後5年間の年平均成長率(CAGR)は21%の予測
- 需要増に備え、継続的なIT電力強化を進行中
KDDIグループの展開状況
テレハウスはグローバルにデータセンターを展開している
- 世界10カ国以上、45拠点以上で展開
- 3000社以上の通信・クラウド関連企業のIT基盤を支えている
おわりに
生成AIの進化とともに、電力と接続性を兼ね備えたデータセンターの重要性は高まっている
KDDIグループは、ロンドンという国際的な要衝において、次世代ITインフラの中核を担う体制を着実に整えつつある
供給電力容量2万2400kW・総工費約600億円…KDDI、ロンドンに新DC
記事3:レノボの「Neptune」水冷サーバーとニデックのCDUがタッグ、AIデータセンターの省エネ化を推進

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズとニデックが、AIデータセンター向け水冷ソリューションで協業を発表した
両社の技術を組み合わせることで、消費電力削減と運用安定性の両立を目指している
協業の目的と省エネ効果
協業の狙いは、水冷サーバーと冷却液分配装置(CDU)を組み合わせたソリューションを通じてデータセンターの環境負荷を低減すること
- 対象は「Neptune」シリーズ水冷サーバー(レノボ)とニデックのCDU
- 消費電力を最大40%削減できると見込まれている
- まず日本市場を起点に、アジア太平洋、将来的にグローバル展開を図る
技術特徴
両社が提供する製品群には、AIサーバーの高熱処理に対応しつつ冷却・運用効率を高める工夫がある
- Neptune第6/第7世代は純水直接液冷方式を採用し、GPU・メモリ・電源など全熱源を冷却できる「100%水冷サーバー」である
- ニデックのCDUはIn Rack型/In Row型を含み、冗長設計やメンテナンス性に優れた設計が特徴
- 冷却ファンの削減、熱の外部放出量抑制により空調負荷も低減可能
市場および運用上の背景
AI活用の拡大に伴い、データセンターの電力課題と冷却負荷が顕在化しており、その対策が急務となっている
- 2025年のAI予算は前年比2.8倍に増加、生成AI導入率は42%に達する見込みである
- データセンターの電力消費が世界の電力使用量の約3%を占め、日本では2030年までに設置施設増加により電力需要が3倍に増えるとの予測がある
- 冷却が消費電力の約40%を占めるため、冷却効率の向上がエネルギー最適化の鍵となっている
おわりに
レノボとニデックの協業は、AI時代におけるデータセンターインフラの「高性能化」と「省エネ化」を同時に進める一手となる
今後は新たなエコシステムとして、水冷サーバーとCDUを含む冷却インフラがデータセンター設計の標準になり得る可能性も示されている
レノボの「Neptune」水冷サーバーとニデックのCDUがタッグ、AIデータセンターの省エネ化を推進
記事4:KDDI、大阪堺データセンターを2026年1月稼働開始

KDDIは2026年1月、大阪・堺に最新AIサーバーを搭載したデータセンターを稼働開始する
再エネ活用や水冷技術などを活かし、高性能かつ環境配慮型のAI基盤を提供する
施設の特徴と技術構成
堺工場跡地を活用し、短期間で大規模DCを構築した点が最大の特徴
- 建物は地上4階建て、延床面積約5万7000㎡
- 電力と冷却設備を再利用し、環境負荷を抑えつつ高性能を確保
- 再生可能エネルギー100%使用、直接液体冷却方式を導入
- GPUはNVIDIA GB200 NVL72など最新AIサーバーを搭載
運用設計とセキュリティ対応
国内拠点ならではの安心性と高度なAI計算処理の両立を図る
- KDDI渋谷DCで確立した水冷設備運用ガイドラインを適用
- 国内運用によりソブリン性を確保し、監視カメラ映像や企業機密も安全に扱える
- 全国DCやモバイル網との連携で多様なデータを集約可能
AIサービスと法人向け展開
高度なAI学習基盤として、法人やパートナー企業に活用の場を提供する
- GPUを法人に提供、AI活用支援を強化
- Googleと連携し、生成AIモデル「Gemini」やNotebookLMを活用したAIサービスを開発・提供
- 「責任あるAI」の推進により、信頼性と法令遵守を両立
コンテンツ提携と個人向けサービス展開
信頼性の高い情報をAIが最適化し、個別ユーザーに提供する仕組みも始動予定
- 2026年春の提供開始を目指し、音声や文章による情報取得を支援
- NewsPicks、ナタリー、価格.com、LDK、マンションノート、mamariなどと連携
- 許諾済みコンテンツをAIが要約し、個人の関心に応じて届ける
おわりに
KDDIの大阪堺データセンターは、AI時代の要請に応える統合的な基盤として設計されている
法人向けの高性能AIインフラとしてだけでなく、一般消費者への安全・信頼性の高い情報提供にも貢献する拠点となる見通し
記事5:小さな不具合が引き起こした大規模インターネット障害、AWSの事案から学ぶ教訓

アマゾンのクラウド事業「AWS」の障害は、二つの自動化されたシステムが同時に同じデータの更新を試みたことから発生した
この小さな不具合が、世界中の大手企業アプリやサービスをダウンさせる大規模な障害へと発展した
障害の発端と影響範囲
事象は10月20日に発生し、発端は二つのプログラムが同じDNSレコードを同時書き込みした「レースコンディション」だった
- 影響を受けたのは、銀行・病院ネットワーク・モバイルバンキング・スマートホーム端末・動画配信サービスなど幅広い
- 例えば、Snapchat、Zoom、Telegramなど、SNSや動画、金融アプリが一時的に利用不能となった
- 発端となったDNS記録の空白が、データベース「Amazon DynamoDB」を停止させ、クラウドサービスの連鎖的混乱を招いた
クラウド依存の構造的リスク
今回の障害は、クラウド基盤への過度な依存が持つ脆弱性を明らかにした
- 単一プロバイダー(特にAWS)への集中が、連鎖障害のボトルネックとなった
- 多くの企業が“クラウド1社依存”の構成をとっており、冗長化やマルチクラウドの備えが不足していた
- 技術的には小さな「自動更新の競合」が原因だったが、影響は世界規模へ拡大した
企業・開発者が取るべき教訓
このような大規模障害を教訓に、組織はインフラ設計を根底から見直す必要がある
- サービス停止時のバックアップ・フェイルオーバー体制を強化する
- 自動化された更新プロセスの競合リスクを検証し、冗長設計と監視体制を整備する
- 「障害が起きない構造」ではなく「起きても影響を最小化できる構造」を意識する
おわりに
たった一つの自動化処理の競合が、インターネットの多くのサービスを停止させる事態を引き起こした今回のAWS障害は、クラウド時代の基盤構築と運用における《見えない危険》を浮き彫りにした
企業は「クラウドの強み」を享受すると同時に、「クラウドの弱点」をも設計に織り込まねばならない
小さな不具合が引き起こした大規模インターネット障害、AWSの事案から学ぶ教訓
記事6:Gmailのパスワード、流出した1億8300万件のアカウントの一部として確認される
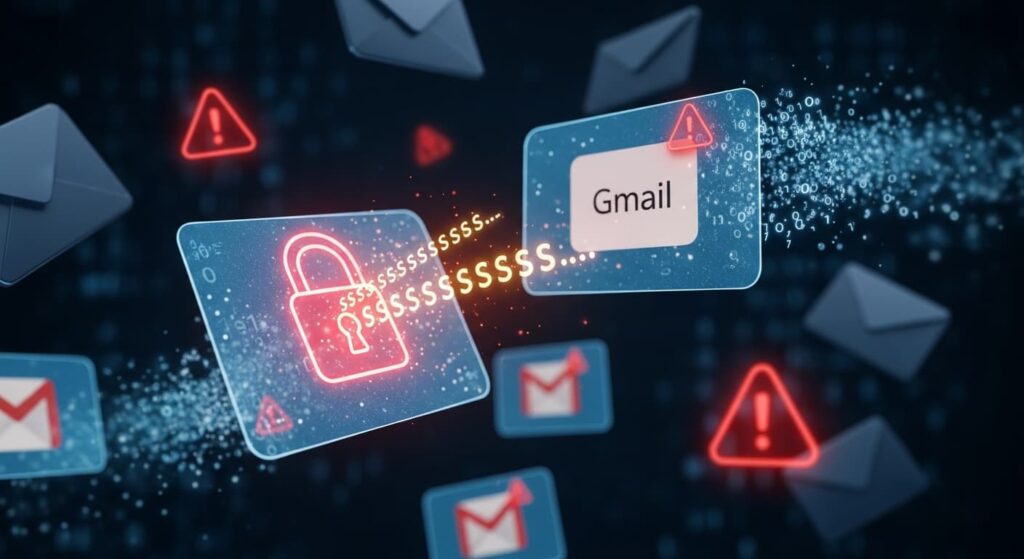
2025年4月に発生した大規模な情報漏えいにより、Gmailを含む多数のアカウント情報が流出していたことが判明した
無料で調査可能な「Have I Been Pwned」での確認が推奨されている
流出の規模と内容
今回の流出は過去にも類を見ない規模であり、1億8300万件以上のアカウント情報が対象となった
- 流出データにはメールアドレス、パスワード、アクセス元のURLが含まれている
- データはスティーラーログとクレデンシャルスタッフィング用リストで構成される
- 確認されたデータの一部はGmailログイン認証情報であった
分析結果と新規性
提供された情報の大半は過去に流出したものであったが、一部は新たに確認されたものだった
- 約9万4000件のサンプルから92%は既知の流出情報だった
- 残り8%、約1400万件超が新しい認証情報と判明
- HIBPでは過去に確認されていないメールアドレスも1640万件見つかった
影響範囲と対処方法
Gmail以外のユーザーも含め、あらゆるユーザーに影響が及ぶ可能性があるため、早急な確認と対処が求められる
- HIBPを利用して自分の情報が含まれているかを確認すべき
- パスワードが漏れていた場合、すぐに変更することが重要
- 使い回しのパスワードがあれば、関連アカウントすべてを変更すべき
おわりに
認証情報の流出は個人情報の悪用やアカウント乗っ取りに直結する重大なリスクである
日頃からパスワードの使い回しを避け、定期的な変更を行うとともに、HIBPなどのツールで漏えいチェックを習慣化すべきである
Gmailのパスワード、流出した1億8300万件のアカウントの一部として確認される
記事7:デジタル庁が後押しする「第三者保守」 コスト削減と投資転換を実現する6つのユースケース

デジタル庁が公開したガイドラインを受けて、ハードウェアの「第三者保守」活用の認知度が高まっている
しかし、日本国内での利用率は海外に比べて依然として低い状況にある
第三者保守とその価値
メーカー保守終了後のハードウェアを、メーカー以外のベンダーが保守を引き継ぐ「第三者保守」は、コスト削減と投資の転換を可能とする手段である
- 海外ではサーバ保守の約48.8%が第三者保守であるのに対し、日本では12.3%と低調である
- コスト削減率として40〜70%という試算も示されている
- メリットとして、契約期間の柔軟性、複数メーカーの機器対応、部品確保の安定性、高度な技術支援が挙げられている
ユースケース6選
第三者保守を実務で活用するための6つの代表的なシナリオが整理されている
- ハードウェア延命戦略
- レガシーシステムのセキュリティ強化
- クラウド移行のための移行期間確保
- 中小企業の情シス人材不足への対応
- 医療機関における専用システム延命
- ?
これらのシナリオを用いて、IT保守コストを抑えてDX投資に振り向ける構造を実現することが可能である
導入上のポイントと注意点
第三者保守の導入にあたっては、以下の点が重要である
- 保守ベンダーの部品在庫・エンジニア体制・マルチベンダー対応力など技術・運用体制の評価が必要である
- 保守切れ(EOSL)機器を使い続けるリスクを管理しつつ、保守費用削減分を“攻めのIT投資”へ振り向ける発想が求められる
- 利用形態・契約期間・保守サービス内容の柔軟性を確保し、必要に応じてリプレースやクラウド移行のための“つなぎ保守”として活用できる
おわりに
第三者保守は、単なるコストカットの手段だけにとどまらず、IT運用構造を見直し、守りの保守から攻めの投資へと転換する契機となる
日本企業・組織が本格的に活用を進めれば、DXの実現加速に向けた現実的な“資金と時間”を捻出できる可能性が高まる
デジタル庁が後押しする「第三者保守」 コスト削減と投資転換を実現する6つのユースケース