
こんにちは、キクです。
本記事は、僕が自己学習で学んだことをブログでアウトプットするシリーズになります。
今回は『サーバの電力関連』について書いていこうと思います。
本記事の内容
それでは、よろしくお願いします。
サーバの電力3段変換について

サーバに届くのは通常100Vや200Vの交流(AC)電源
しかし、サーバ内部の部品(CPUやメモリなど)は直流(DC)でないと動かない
そのため、サーバでは以下のような3段階の電力変換が行われている
1. AC → DC(交流 → 直流)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 変換の内容 | データセンターから送られてくるAC(交流)電源を、DC(直流)電源に変換 |
| 担当する部品 | 電源ユニット(PSU) |
| なぜ必要? | サーバ内部の電子部品は、交流ではなく直流でしか動かないため |
| 事例 | 100Vや200Vの交流が12Vや48Vの直流に変換される |
2. DC → 低圧DC(5Vや3.3Vなど)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 変換の内容 | 12Vや48Vといった比較的高い直流電圧を、より低い電圧(例:5V, 3.3V)に変換 |
| 担当する部品 | VR(Voltage Regulator:電圧レギュレータ)などの回路 |
| なぜ必要? | ストレージやチップによって使う電圧が違うため、それぞれに合わせた電圧に分けて供給 |
| 事例 | 12V から HDD用に5Vやマザーボード用に3.3Vに変換するなど |
3. 低圧DC → 超低圧DC(1V以下)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 変換の内容 | さらに一部の重要部品(CPUやメモリなど)向けに、1V以下の超低電圧に変換 |
| 担当する部品 | PMIC(電源管理IC)やVRM(Voltage Regulator Module) |
| なぜ必要? | 高性能なCPUなどは非常に低い電圧で動作し、それを正確に保つ必要があるため |
| 事例 | CPUやGPU、メモリなどのために0.9Vや1.2Vへに変換 |
ポイントは、CPU/GPUは高電圧に弱いので、段階的に落とすのが必須ということ
「電圧を下げると電流が上がる」の意味をちゃんと理解する
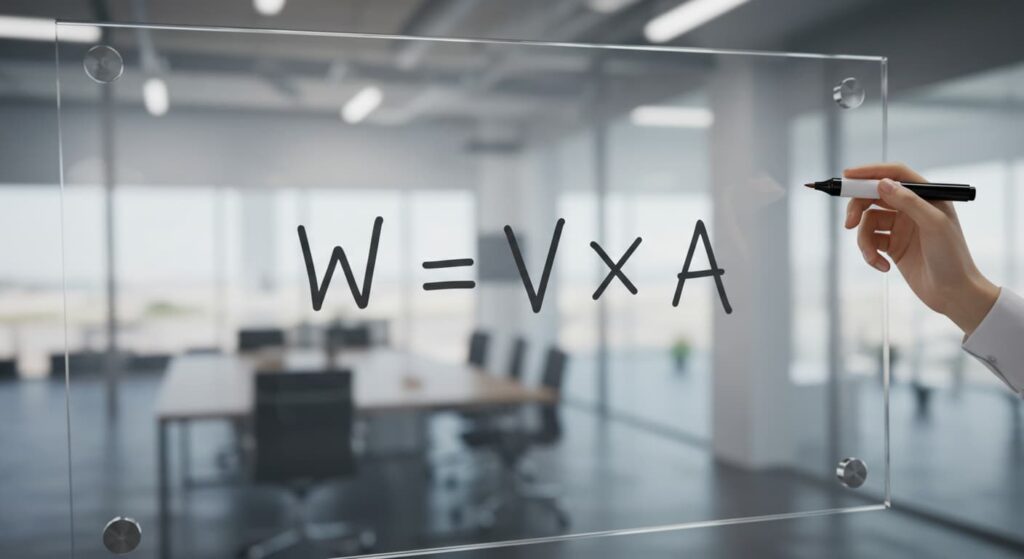
改めて、電力を算出するための基本式は以下の通り
電力(W)= 電圧(V) × 電流(A)例えば、同じ300Wを供給する場合には次のようなことが言える
- 電圧48Vの場合:電流6.25A
- 電圧12Vの場合:電流25A
同じ電力(W)を提供したい場合には、電圧(V)を下げると電流(A)を上げる必要がある
疑問:電圧を下げることで電流を上げてるのは誰?
電源ユニット(PSU)は、ただ電圧を安定して出しているだけ
電流をどれだけ流すか決めているのは、CPUやGPUなどの“負荷側”と言える
すなわち、負荷側が必要とする分だけ、電流が自然に流れる(いわば“引っ張る”)
水道に例えると
- 蛇口 = PSU
- 電圧 = 水圧
- 電流 = 水の量
- 使う人 = 負荷
水道からどれだけ水を流すかは、蛇口を捻った量によって変化する
そして、この蛇口を捻るのは「使う人 = 負荷」ということになるので、例えばCPUがたくさん蛇口を撚ればそれだけ水(電流)が流れることになる
サーバの消費電力に「上限」はあるのか?

GPUサーバなどが5kWを使うような時代になっても、電力は無限に増やせるわけではない
実際には、いろいろな制限(ストッパー)がある
ここでは、「サーバ内部」→「PSU」→「データセンター」の順で整理
1. サーバ内部での制限
VRMの限界
流せる電流に上限あり(例:100A)
超えると発熱・焼損リスク
VRMとは
Voltage Regulator Module
CPUやGPUなどのプロセッサに対して、正確で安定した低電圧を提供するための電源回路
基板配線の制限
銅箔パターンにも太さや許容電流の限界がある
部品のTDP制限
CPUやGPUには設計上の最大電力(TDP)があり、それを超えると動作保証外
2. PSU(電源ユニット)での制限
出力W数の上限
PSU自体の最大容量(例:2400W)があり、それ以上は供給不可
各出力ライン(12Vなど)の制限
たとえば「12Vで最大83Aまで」などの制限がある
ケーブルやコネクタの限界
C13は10A、C19は16〜20A程度までなどの制限がある
それ以上は危険
3. データセンター側での制限
ラックPDUの容量
1回路で20A程度、200Vなら4kWが限界
5kWサーバを積んだ場合、それだけで枠がいっぱいになってしまうことも
冷却能力の上限
空調・エアフローで冷やせないと運用不可
電力よりも熱がボトルネックになることも多い
配電盤・UPSの設計容量
分電盤、変圧器、UPSなどもそれぞれ設計上の上限がある
契約電力(kVA)の上限
データセンター全体が契約している電力量(例:1000kVA)を超えると、もう増やせない
12Vと48V給電の違い
最初は「どうせ最終的に1Vに落とすなら、12Vでも48Vでも同じでは?」と思った
しかし、「どの地点で、どのくらい電流を流すか」と「変換の効率と熱の分布」など違いはある
GPUからサーバの末端までを「12V系」「48V系」で比較して整理
12V給電の場合
概要
- PSUが12Vで出力し、各部品(VRM)に12Vが供給される
- VRMで12V → 1Vに変換し、GPUやCPUに供給
特徴
- 12Vから1Vへの変換は電圧差が大きいため変換効率が低い
- 1Vで300W使うGPUには 12Vラインで25A以上流れる
- 12V電源ライン上での発熱・ロスが大きくなる
48V給電の場合
概要
- PSUが48Vで出力し、VRMに48Vを供給(または途中でDC-DCで12Vに変換)
- GPU直近のVRMが 48V → 1V に変換
特徴
- 48V→1Vの変換はマルチフェーズ対応の高効率VRMで行われる
- 同じ300Wでも 48Vラインなら6.25Aで済む
- 電流が小さいため、ケーブルや基板の発熱・ロスが大幅に減る
整理
1Vへの変換は最終的に必要だが、そこまでの電圧が高いほど有利
- 12Vで運ぶと:電流が大きく、発熱・配線負荷・電力ロスが増える
- 48Vで運ぶと:電流が小さく、効率的で冷却・設計の自由度が高い
つまり「電圧が高いまま遠くまで運び、必要な場所で落とす」のが効率的ということ
これはまさに電力会社が送電線で高圧送電するのと同じ理屈
GPUサーバなど電力が大きい用途では、48V給電が圧倒的に有利
「12Vライン」や「48Vライン」ってどういう意味?
ラインとは、特定の電圧が流れる回路や配線の系統のことで、例えば次のようなものがある
- 12Vライン:PSUの12V出力ケーブル、基板上の12V経路、VRMまで含めた一連の供給網
- 同様に、5Vライン、3.3Vライン、48Vラインも存在する
マルチレール構成だと、CPU用・GPU用などに分けられていることもある
なぜ48V給電が注目されているのか?
GPUサーバやAIサーバのように電力密度が高い構成では、12V給電の限界が見えてきた
48V給電にすることで以下のようなメリットがある
- 電流が1/4になり、発熱・ロスを大幅削減
- 配線が細く軽くなり、設計の自由度が高まる
- PSU・VRMの負荷軽減、全体として効率が向上
OCP(Open Compute Project)などでは48V給電を前提としたラック構成も標準化が進んでいる
まとめ
サーバの電力供給は、単なる「電気を流す」話ではなく、電圧・電流・電力のバランスと、それをどう安全かつ効率的に制御するかという設計の話だった
特にGPUサーバのような高電力機器では、電流をどう抑えて、ロスや発熱をどう最小限にするかが大きな課題になる
その解決策の一つとして、48V給電のような新しいアプローチが採用されてきている。
今回の整理を通じて、電源の基本から現場での設計まで繋がりが見えてきたので、今後は実際の電源ユニットやデータセンター設計の事例についても意識して、より現実的な視点を深めていきたい