
こんにちは、キクです。
本記事では、僕が今週読んだIT系のニュースについて「振り返り」と「まとめ」を目的として整理していきます。
本記事の内容
日々の収集録

本記事でご紹介する記事とは別で朝イチ情報収集習慣として今週整理した記事も紹介させてください。
読んだ記事
- AIデータセンターに必要とされる設計・製品とは、シュナイダーエレクトリックのニルパ・チャンダー氏に聞く
- GPT-5が公開されたが、このAIは明らかに汎用人工知能でも人工超知能でもない
- 次世代AI「GPT-5」の実力は? ChatGPTで使ってみた 旧モデル「GPT-4o」「o3」と使用感を比較
- AIインフラ「InfraWaves」がシリーズAで20億円を追加調達、中国LLM競争を支える“縁の下の力持ち”
- 生成AIがついに実戦投入 革新的なマルウェア「LAMEHUG」のヤバイ手口
- SANDISK、256TBの大容量SSD。データセンター向け
読んだ記事
- NVIDIAがプロ向けグラボ「RTX PRO 2000 Blackwell」「RTX PRO 4000 Blackwell SFF」を発表 2025年後半に発売予定
- なぜGPT-5で大混乱?無料は最新、有料は旧モデル選択の謎仕様に
- 前澤友作氏「一緒に国産SNS作りませんか?」とXで呼びかけ 掲げた「理想」は5つ、動機は詐欺広告か
- クラウドでもHDDでもなく「オンプレミス×SSD」を選んだRed Lobsterの理由
読んだ記事
- PJMが2030年までにデータセンター需要で30GWのピーク負荷増加を報告
- NVIDIAオフィスに女子中高生が集結!革ジャンCEOから最新GPU、AIファクトリーまで
- ChatGPTにアップデート ~「GPT-4o」が既定で再利用可能、「GPT-5」のモデル選択が変更に
- 爆速開発AI「バイブコーディング」が怖すぎるワケ、見落とし注意の“ある欠陥”とは
- L・トーバルズ氏、カーネル開発者に痛烈な一言:「ゴミを送るな、世界が悪くなる」
ITニュース系
記事1:「それでもオンプレ回帰は起きない」データセンター調査から浮かび上がる“その理由”

世界のデータセンター市場では、クラウド事業者(ハイパースケーラー)の支配力が強まり続けている
AI需要やGPU導入でオンプレ環境も一部拡大しているが、クラウド利用量は増加傾向が続く
オンプレ回帰が起きない背景
AI需要増でもクラウド依存が加速
- オンプレミスのコンピューティング能力は全体の3分の1強
- クラウド費用急騰にも関わらず、AIワークロード対応でクラウド利用が増加
- 2030年にはハイパースケーラーが容量の60%以上を占有、オンプレは22%に低下見込み
- オンプレ容量は横ばいから微増に転じたが、全体の比率は縮小傾向
ハイパースケーラーの支配力拡大
AI運用に最適な立場と巨額投資
- AWS、Microsoft、Google Cloudで全ハイパースケーラー容量の約60%を占有
- 2025年第1四半期のデータセンター投資額は前年比53%増
- 3社合計で年間2,500億ドル超の設備投資を計画
- 施設数は前年比53増の1,189に拡大
オンプレが不利な市場環境
高騰する賃料と逼迫する空室率
- 米主要地域のデータセンター空室率が過去最低に
- 賃料は前年比最大15%上昇
- ハイパースケーラー以外の事業者は市場逼迫で拡張が困難
まとめ
AIワークロードや大規模データ処理に対応するには、巨額投資とスケールを持つハイパースケーラーが有利であり、クラウド利用は拡大傾向を維持している
一部でオンプレ容量は増加しているものの、比率は縮小し、オンプレ回帰の兆しは見られない
用語メモ
ハイパースケーラー
AWSやAzure、Google Cloudなど、巨大規模のクラウド事業者
OPEX(Operating Expenditure)
運用経費
CAPEX(Capital Expenditure)
設備投資費用
「それでもオンプレ回帰は起きない」データセンター調査から浮かび上がる“その理由”
記事2:AI需要でデータセンター空室率が急低下_劇的な逼迫と高騰の背景
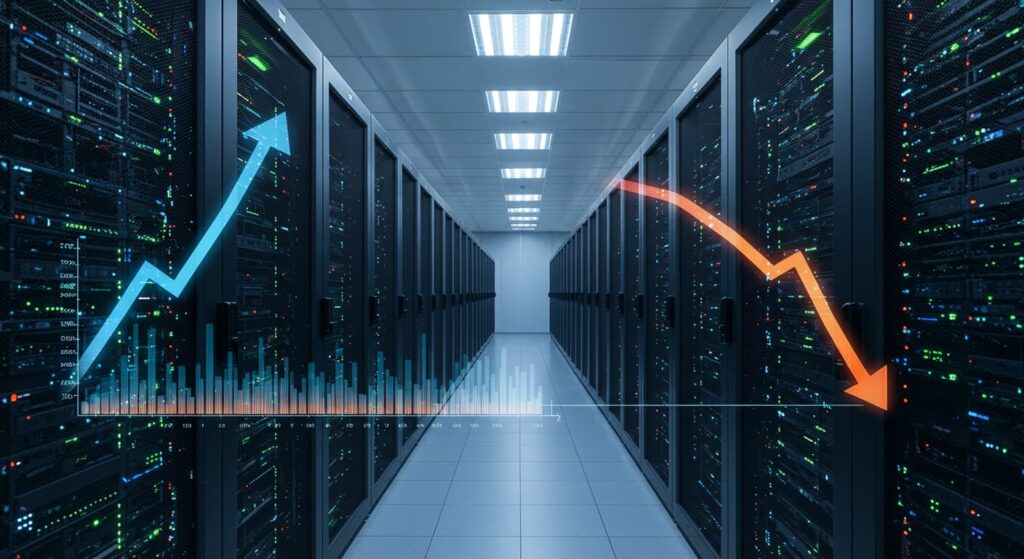
AI導入の加速により、データセンターの空室率が急低下し、賃料が大幅に上昇している
背景には、クラウド需要の拡大と電力供給制約がある
需要急増と空室率低下
米主要市場で深刻な逼迫が発生
- 2025年第1四半期の米主要市場の平均空室率は世界平均6.6%の約3分の1
- 前年比2.1ポイント減少し、AIとクラウド需要が主因
- 空き容量を持つ事業者はプレミアム価格を設定
賃料高騰の要因
高需要と建設コスト上昇が直撃
- ノーザンバージニアは前年比15%、シカゴは14.7%賃料上昇
- 2013~2020年は下落傾向だったが2023年から急騰
- GPU導入による電力需要増で、電力確保が立地選定の重要条件に
建設ラッシュと容量不足
新設も追いつかない需要
- AWS、Microsoft、Google Cloudが総額2,500億ドル以上を投資
- 北米主要4都市で新規建設が前年比43%増の過去最高
- 新容量は稼働直後に消費され、先行契約も活発化
事業者の対応
早期調達と土地確保で需要に備える
- CoreSiteはシリコンバレーやニューヨークなどで追加容量を継続稼働
- 土地の先行取得や早期調達で顧客需要に対応
- 建設遅延により稼働が2027年以降にずれ込む案件も発生
まとめ
AIとクラウド需要がデータセンター市場を逼迫させ、空室率低下と賃料高騰を招いている
新設計画は活発だが、電力供給や建設遅延が課題となっており、需給ギャップは短期的に解消しにくい状況にある
用語メモ
コロケーション
複数の企業がデータセンター施設を共有利用する形態
キャリアニュートラル
特定の通信事業者に依存せず、複数の通信回線を利用できるデータセンター
AI需要でデータセンター空室率が急低下_劇的な逼迫と高騰の背景
記事3:エヌビディア、AIチップに「キルスイッチ」や「バックドア」が仕掛けられれば「アメリカの技術に対する信頼が損なわれる」と警告(海外)

エヌビディアは、AIチップへの「キルスイッチ」や「バックドア」の導入に強く反対し、これはアメリカの技術に対する信頼を損ない、大きなリスクを招くと警告した
エヌビディアの主張
政府によるチップ監視機能は不適切
- GPUにキルスイッチやバックドアを搭載すべきではないと明言
- バックドアは外部から所有者不在でチップ制御が可能になり、技術全体を脆弱化させる
- 永久的な欠陥となり、経済や安全保障に取り返しのつかない損害を与える可能性
中国での懸念と対応
H20チップを巡る安全性議論
- 中国当局がH20チップのバックドアリスクを懸念し会談を要請
- 同社は中国市場向けH20の出荷を再開予定(米政府の輸出承認を受けて)
他社事例との比較
アップルの反バックドア姿勢との共通点
- Appleはソフトウェアバックドアを「ソフトウェアのがん」と批判
- 2016年のFBI要請や2025年の英政府命令にも抵抗
- エヌビディアも「ユーザーが制御できる機能」と「ハードウェアのバックドア」は別物と強調
AI業界への影響
主要AI企業が依存するGPUの信頼性問題
- OpenAIやMetaなどが同社GPUでAIモデルをトレーニング・運用
- ハードウェアレベルの監視機能導入は業界全体のリスク要因
まとめ
エヌビディアは、AIチップへの政府主導の監視機能導入を強く拒否し、ユーザー制御を超える仕組みは重大な欠陥になると警鐘を鳴らしている
技術の信頼性と国家安全保障を守るには、透明性と利用者主導の設計が不可欠である
用語メモ
キルスイッチ
遠隔操作で機器を停止・無効化する機能
バックドア
通常の認証手順を経ずに機器やソフトへアクセス可能にする仕組み
H20チップ
エヌビディアが中国市場向けに設計したAI向けGPU
エヌビディア、AIチップに「キルスイッチ」や「バックドア」が仕掛けられれば「アメリカの技術に対する信頼が損なわれる」と警告(海外)
記事4:Intel低迷でSamsungが笑う?パッケージングのエース級人材が移籍

Intelの人員削減が続く中、半導体パッケージング分野のトップ人材がSamsungへ移籍し、業界で注目を集めている
背景にはIntelの研究開発縮小やコスト削減があり、競合や新興企業への人材流出が加速している
Samsungへの人材流出
ガラス基板技術やEMIBの第一人者が移籍
- Intelで17年の実績を持ち、約500件の特許を保有するGang Duan氏がSamsung Electro-Mechanics Americaの副社長に就任
- EMIBやガラス基板など先進パッケージング技術の開発に貢献し、2024年にIntelの「Inventor of the Year」を受賞
- Intelのガラス基板研究縮小が移籍の背景にある可能性
ガラス基板技術の重要性
次世代AIチップに不可欠な基盤
- 低熱膨張率、高平坦性、低誘電損失が特長
- Samsungは2025年にパイロットライン構築、2027年に量産開始予定
- Intelは2023年に発表後、2024年に開発規模を縮小し外部調達方針へ
新興企業への転身
元Intelエンジニアが続々と起業
- AheadComputing:RISC-Vベースの高性能CPUコアを開発、創業メンバーはIntel在籍合計約100年の経験を持つ
- Mihira AI:GPUクラウド配信「Project Endgame」を起源とする企業、NVIDIA CUDAやAMD ROCmに対抗する基盤構築を目指す
- その他、インドのInfinipackやFlexAIなど半導体・AI関連スタートアップが誕生
組織変革と新陣営
人材流出と同時に新幹部を迎え入れ
- Greg Ernst氏をCROに任命、他3名のシニア幹部を採用
- OpenAI支援のRain AI出身やGoogleモバイルSoC設計者など、多様な経歴の人材が合流
- 組織スリム化と機動力強化を目指すが、優秀人材流出は競合の追い風に
まとめ
Intelは人員削減と研究縮小によって重要技術の担い手を失い、Samsungや新興企業への人材流出が進んでいる
一方で新幹部採用による再編も進行中だが、競合にとっては技術力強化の好機となっており、今後の半導体競争は人材獲得戦が一層激化するとみられる
用語メモ
EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)
複数チップを高密度かつ低レイテンシで接続するIntel独自のパッケージング技術
ガラス基板
有機基板に代わる新素材で、AIやHPC向け高性能チップの基盤として期待される
RISC-V
オープンソースの命令セットアーキテクチャで、カスタマイズ性と低コストが特長
Intel低迷でSamsungが笑う?パッケージングのエース級人材が移籍